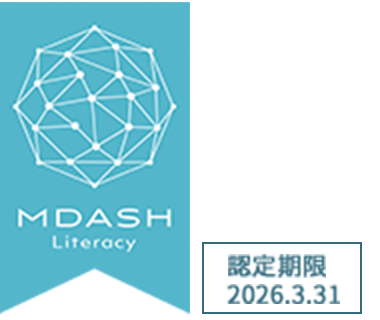2025年度「AI技術×〇〇」研究デザインプロジェクト支援経費公募を開始します
学内のデータサイエンス文化醸成をより拡充させるため, AI技術を様々な分野で活用することを目的とした研究を対象に支援する「AI技術×〇〇」研究デザインプロジェクトを公募します。
各種様式
| ※申請の際には,申請書(様式1),審査(ヒアリング)日程調整表(様式2)に加え, 任意様式の審査(ヒアリング)用のスライド資料を提出する必要がありますのでご留意ください。 |
2025年度「AI技術×〇〇」研究デザインプロジェクト支援経費公募要領
*本公募要領は,公募開始時の 4月2日(水)まで予算金額,スケジュール等が変更される場合があります。
1.本経費の背景と目的
本学においては,これまで,第5期科学技術基本計画におけるSociety5.0の提唱や,第4次男女共同参画基本計画における女性活躍促進の方向性に基づき,「データサイエンス文化醸成のためのAI技術研究交流促進プロジェクト」(2019年度~2021年度),「AI研究デザインプロジェクトスタート支援」(2020年度~2022年度),「AI研究デザインプロジェクト支援経費」(2021年度~2023年度)等,AI技術の適用が可能なデータを取り扱う研究者とAI技術の研究を行っている研究者による共同研究を推進してきた。また,組織としても,2020年度に「情報・データ科学教育センター」や「Diversity×AIラボ」が設置され,データサイエンスの重要性はますます高まっている。
ついては,学内のデータサイエンス文化醸成をより拡充させるため, AI技術を様々な分野で活用することを目的とした研究を対象に支援する「AI技術×〇〇」研究デザインプロジェクトを2023年度より開始し,2025年度も公募することとなった。
また,本学では,中期目標・計画に掲げているように女性研究者の研究を支援する取り組みを進めており,上記の「Diversity×AIラボ」についても女性研究者を含む研究チームとAI技術の融合を促進し,研究活性化・効率化による研究力強化を図ることとしている。これらを踏まえ,本プロジェクト支援経費においては,女性研究者を含むグループの部門を設け,研究費の面において,女性研究者を積極的に支援することも目的の一つとしている。
2.部門について
本プロジェクトは,①一般グループと②ダイバーシティグループの2部門で構成され,審査時に審査員によって,部門を決定する。
研究代表者が女性もしくは,グループに女性研究者が含まれている場合には,②ダイバーシティグループとして採択することがある。
3.経費の申請条件及び支援内容
本プロジェクトへの申請は,以下の条件等によるものとする。
(1)本学の研究者のうち,AI技術を応用的に活用する研究を行う者を対象とし,自身のこれまでの研究または,これから新規に行う研究において,AI技術を用いた研究内容であること。(AI技術を様々な分野で活用することを目的としているため,例えば,「AI技術×微生物」,「AI技術×医療データ」,「AI技術×教育」等を想定している。)
なお,研究内容について特段の実績がなくても,今後取り組む予定のある研究についても申請することができる。
(2)学内のデータサイエンス文化の醸成をより拡充し,研究者相互のやりとりを活性化させることも目的の一つとしているため,複数人(2人以上)のグループで申請すること。大学院生・学部生や学外者を加えることは差支えないが,研究代表者及び主たるメンバーは学内の研究者でなくてはならない。特に学外者の研究者を含む場合でも,分担金とせず,本学の予算として執行すること。
(3)過去に下記のプロジェクトに研究代表者として申請し,採択された者は,再度研究代表者として申請することはできない。
・「データサイエンス文化醸成のためのAI技術研究交流促進プロジェクト」(2019年度~2021年度)
・「AI研究デザインプロジェクトスタート支援」(2020年度~2022年度)
・「AI研究デザインプロジェクト支援経費」(2021年度~2023年度)
・「AI技術×○○」研究デザインプロジェクト支援経費
(2023年度~2024年度,2025年度,2024年度~2026年度)
(4)過去に下記のプロジェクトに研究代表者として申請し,採択された者が,再度研究代表者として申請する場合の支援期間は,最大2年までとする。
・「AI研究デザインプロジェクトスタート支援経費」(2022年度)
申請上限額は設けないが,総額3,000 千円/年(予定)に対し,採択件数は①②の部門あわせて3 件程度とする。
また,支援期間は最大3年間とする。なお,次年度以降は大学の予算の状況により,配分が減額もしくは,配分されない可能性があることに留意すること。(年度ごとに必要経費について確認する。)
4.審査
審査については,ヒアリングにより選定を行う。
(申請多数の場合は,ヒアリング審査に先立ち,書面審査を行う場合がある。)
・ヒアリングは,研究代表者が必ず出席し,説明をする必要がある。
(研究代表者以外の出席は,必ずしも必要ではない。研究協力者等の出席が必要であれば,ヒアリングに出席しても構わない。)
・ヒアリングはオンライン(GoogleMeet)で行う。資料をスムーズに共有できるよう,事前に設定やネットワーク環境等を確認しておくこと。
5.経費
(1)本経費の積算項目は,研究を実施する上で必要とする経費(備品・消耗品費・諸謝金・旅費等)について積算可能とする。
(2)本経費は年度ごとに配分された経費を年度内に執行するものとする。次年度への繰り越しはできない。また,予算残額が発生する場合は,可能な限り早期に返納するものとする。
6.研究(代表)者の責務
- 毎年度,成果報告会を開催する。研究(代表)者は研究進捗状況等の報告を行うこと。経費補助期間終了後は,同報告会で最終成果報告を行うこと。原則全ての報告会に出席し,発表を行う必要がある。
- 年度終了毎に,研究進捗状況報告と支援経費執行状況報告を提出すること。(様式は別途通知。)
- 申請書にある「プロジェクト期間終了時における研究成果目標」を達成できるよう努力すること。上記の成果報告時に,年度ごとの状況を報告すること。その際,目標達成に向けて進歩がない,もしくは,計画が変更されているようであれば,次年度以降の配分予算に影響する場合がある。
- プロジェクトで得られた研究成プロジェクトで得られた研究成果の論文投稿,学会発表に際しては,「本プロジェクトでの経費支援によるものであること」(YU AI project of Center for Information and Data Science Education)の記載を行うこと。
- 本学におけるダイバーシティ推進及び研究広報活動を行うこととなった場合は,協力すること。
7.提出書類
(1)2025年度「AI技術×〇〇」研究デザインプロジェクト支援経費申請書(様式1)
(3)パワーポイントを用いた審査(ヒアリング)用のスライド資料(様式任意)
枚数は特に指定しないが,ヒアリング時の発表時間は10分程度を想定。
8.申請書提出期限
(1)及び(2)・・・ 令和7年4月25日(金)正午(厳守)
(3) ・・・・・・・ 令和7年5月2日(金)正午(厳守)
9.申請書等提出先
情報・データ科学教育センター(学生支援部教育支援課教育連携係)
E-mail:ga110@yamaguchi-u.ac.jp 内線:5233
上記7の書類をメール添付にて提出。
10.本経費申請に関する今後のスケジュール(予定)
公募開始 令和 7年 4月 2日(水)
提出期限 令和 7年 4月 25日(金)正午(厳守)
ヒアリング審査 令和 7年 5月 9日(金)~ 5月30日(金)
(申請多数の場合は,ヒアリングに先立ち書面審査を行う場合がある。)
経費支援結果通知 令和 7年 6月上旬
審査上の視点
| 審査区分 | 審査に係る主な視点 |
| 研究計画 | 研究活動計画(ロードマップ)に具体性はあるか。 |
| 研究内容 | ・実際に測定・採取・収集等された,いわゆる実データを用いて研究を実施す る内容となっているか。 ・データにAI 技術を適用することで,新たな発見や価値・サービスの創出が 見込まれる研究内容となっているか。 ・研究グループの編成による多様性が研究内容に反映されているか。 |
| 研究体制 | 研究グループの編成は適切か。また,実データにAI 技術を適用して成果が 出せるように,構成者の連携の仕方に工夫がなされているか。 |
| 研究成果 | 社会への還元,実用化等の研究成果が見込めるものとなっているか。 より具体的な研究成果が見込めるか,またそれを達成できるか。 |
Q&A
Q:申請するグループにAIを専門に研究する研究者を含む必要があるか?
A:研究グループに必ずしもAI技術を専門として研究する研究者,技術者を含む必要はありません。
ただし,研究に際し,AI技術を活用している必要があります。
Q:「AI研究デザインプロジェクトスタート支援経費」(2022年度)に採択された者が代表者として申請する場合は,経費支援が最大2年となっているが,研究計画は,最大3年,2年どちらで出すべきか?
A:経費支援に合わせた期間での研究計画の申請をお願いいたします。
このため,「AI研究デザインプロジェクトスタート支援経費」(2022年度)の研究代表者の方が申請する場合は,研究計画,経費支援について,最大2年としてください。
なお,研究期間が短いことにより,採択が不利になることはありません。