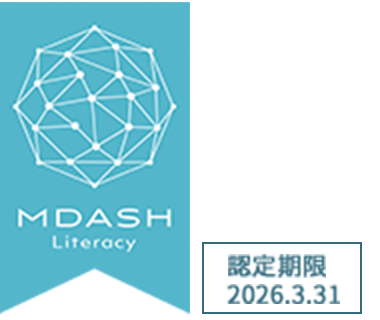[ 第51号 ]日本ガイシ株式会社/中国・四国地区大学教育研究会/AI関連研究プロジェクト成果報告会/レノファ山口FCファンマーケティングプロジェクト
─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…
山口大学情報・データ科学教育センター メールマガジン
第51号・2025年6月発行
─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…
教職員、学生の皆さま、こんにちは!
情報・データ科学教育センターです。
「BANI(バニ)という言葉をご存知でしょうか?
「VUCA(ブーカ)」という言葉は耳にしたことがあるかもしれません。
変動し、不確実で、複雑で、曖昧な現代社会を表す言葉として広く浸透
しました。しかし、カリフォルニア大学教授のジャメ・カシオ氏が提唱
するBANIは、このVUCAに代わる、より現代に即した概念として注目
されています。BANIはBrittle(脆弱性)、Anxious(不安)、Non-Linear
(非線形性)、Incomprehensible(不可解さ)という4つのキーワードの
頭文字を組み合わせて作られています。
このBANIの概念は、現代の私たちの生活に深く入り込んでいる生成AI
によって、その特徴をより鮮明に示しています。ここでは生成AIが
もたらす「不安」と「不可解さ」に焦点を当ててみましょう。
ChatGPTの登場以来、生成AIの活用は急速に広がり、多くの人々が
その効率性と生産性向上に期待を寄せています。しかし、その一方で
AIの導入・普及に対する不安を抱く声も少なくありません。実際に
アメリカで行われたある調査*1では、AIの導入によって特定の職種が
時代遅れになること(75%)、給与への悪影響(72%)、AI技術の活用
方法を知らないために昇進の機会を失うこと(67%)など、広範な
不安感が示されています。
さらに、AIの大きな特徴は「不可解さ」です。いわゆるブラックボックス
と呼ばれるように、AIがなぜ特定の出力を出すのか、その推論過程は
人間には理解しにくいものです。事実と異なる情報を生成する「ハルシ
ネーション」や、わずかな入力で結果が変わる「予期せぬ出力」、そして
倫理的な問題を引き起こすバイアスなど、AIの振る舞いが把握しにくい
点が挙げられます。
変化の速い現代において、私たちはBANIという視点から現状を理解し、
この混沌とした時代を乗り越える方法を考える必要があります。
まずは、身近なAIの「不安」や「不可解さ」と向き合うことから始めて
みませんか?
*1 EY, “How organizations can stop skyrocketing AI use from fueling anxiety,”
https://www.ey.com/en_us/consulting/businesses-can-stop-rising-ai-use-
from-fueling-anxiety
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
データサイエンスやDXに関する取り組みのご紹介
「日本ガイシのDX推進」
日本ガイシ株式会社 デジタル変革推進部 データ活用推進G
グループマネージャー 平島 大介 様
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
日本ガイシ株式会社(本社:名古屋市)は、独自のセラミック技術でカーボン
ニュートラルとデジタル社会に貢献することを目指し、モビリティ、エネルギー、
IoT、産業など幅広い分野で活動しています。より快適な社会の発展に向けて
新たな価値創造に挑戦します。
当社は「DX推進」を全体変革の推力と位置づけ、市場競争力や生産性を高め、
新たな価値創造を目指しています。
工場では、全工程のデジタル化を進めることで生産性を大幅に向上させ、データ
ドリブンなモノづくりを推進しています。また、研究開発分野では、創立以来
100年にわたり蓄積してきた実験データをAIと組み合わせた「MI(マテリアル・
インフォマティクス)プロジェクト」に取り組み、高機能材料の創出を目指して
います。
さらに、生成AIスタートアップとの連携により、社会課題(ニーズ)と当社保有
技術(シーズ)を掛け合わせることで、早期の新事業創出を図っています。
▼ NGKグループのDXについてはこちら ▼
https://www.ngk.co.jp/dx/
▼ データサイエンティスト職社員様のご紹介 ▼
https://www.ngk.co.jp/recruit/university/person/person-07.html
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第72回中国・四国地区大学教育研究会「情報教育分科会」報告
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
令和7年6月14日(土)、第72回中国・四国地区大学教育研究会が島根大学を
当番校としてオンラインで開催されました。本研究会では、「教養教育と総合知
の涵養」をテーマに、基調講演、大学事例報告、研究・教育実践の発表が行われ
ました。情報教育分科会では、「大学での数理・データサイエンス・AI教育の
現状と今後の展望」をテーマに文部科学省と各大学の取り組みが紹介されました。
最初に文部科学省の今川新悟専門官より、「数理・データサイエンス・AI教育プロ
グラム(MDASH)認定制度」の概要や認定状況について説明があり、国としての
推進状況が示されました。
続いて、各大学での具体的な取り組みが紹介されました。愛媛大学の原本博史教授
からは、2024年度にMDASH応用基礎レベルに認定された同大学の教育実践が報告
されました。全学部の学生が共通教育科目で履修できるよう開講し、PBLを重視
している点が強調されました。川崎医療福祉大学の兵藤史武講師は、担当する
「データサイエンス入門」の授業内容を紹介されました。企業から提供される
学内の自動販売機データを用いて統計分析の初歩を学ぶという、学生にとって
身近でユニークな実践例が注目を集めました。
今回の分科会は、文部科学省の推進状況から各大学の具体的な教育実践まで、
数理・データサイエンス・AI教育の「今」を知る貴重な機会となりました。
学生の実践的なスキル習得に向けた、各大学の工夫が印象的でした。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和7年度AI関連研究プロジェクト成果報告会報告 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
令和7年6月9日(月)、12日(木)に、情報・データ科学教育センター主催の
「令和7年度AI関連研究プロジェクト成果報告会」をオンラインで開催しました。
本センターでは、これまで、「データサイエンス文化醸成のためのAI技術研究
交流促進プロジェクト」(2019年度~2021年度)、「AI研究デザインプロジェクト
スタート支援」(2020年度~2022年度)、「AI研究デザインプロジェクト支援経費」
(2021年度~2023年度)等を通じ、AI技術の活用が見込まれる分野の研究者と、
AI技術そのものの研究を行う研究者による共同研究を推進してきました。
2023年度からは、こうした取り組みをさらに発展させるべく、「AI技術×〇〇」を
テーマに、様々な分野でのAI活用を支援する研究デザインプロジェクトを開始して
います。
今回の報告会は、これらのプロジェクトにおける共同研究の過程や成果、得られた
知見を学内で広く共有し、データサイエンス文化のさらなる醸成を図ることを目的に
開催したものです。
報告会では、以下の6つのプロジェクトについて発表が行われました。(敬称略)
・「頚動脈エコー情報に基づく脳循環予備能推定システムに関する研究」
大学院医学系研究科 助教 河野亜希子
・「CALM心理療法支援のための音声・自然言語処理AIの活用」
大学院医学系研究科 教授 中津井雅彦
・「川崎病個別化医療システムを用いた乳幼児突然死予防への挑戦」
大学院医学系研究科 講師 岡田清吾
・「経験情報の記銘システム解明:リップル発火と情報エントロピーの動的変化」
大学院医学系研究科 教授 美津島大
・「機械学習を用いた統計的因果推論のマーケティングへの適用」
大学院技術経営研究科 教授 石野洋子
・「電子聴診器を用いたAI診断・循環器病スクリーニングシステムの開発」
医学部附属病院 助教 小室あゆみ
報告会には、学生や教職員合わせて20名以上の方にご参加いただきました。
参加者の皆さんは、各研究発表に熱心に耳を傾け、発表後には活発な質疑応答と
討論が繰り広げられました。自身の知見を深め、新たな視点を得るための有意義
な時間となったことと思います。
当日、ご出席できなかった方のために、録画ビデオをMoodleを通じて
学内限定で公開しています。ぜひご覧ください。
▼ AI関連研究プロジェクト成果報告会(2025年度)録画ビデオ ▼
https://mdcs5.cc.yamaguchi-u.ac.jp/moodle/course/view.php?id=78867
※閲覧期間:2025年7月31日(木)まで
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
レノファ山口ファンマーケティングプロジェクト活動
学生対象アンケート調査ご協力のお願い
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
前号でお知らせしましたが、現在、レノファ山口ファンマーケティングプロジェクト
の活動の一環として、山口大学生を対象としたアンケートを実施しています。
このアンケートでは主に、山口大学生がどのようなジャンルに興味があり、
どのようなところに惹かれるのか、レノファ山口に対してどれほど興味、関心を
持っているか、さらに趣味や休日に何をしているかについての質問をします。
レノファ山口が好きな方だけでなく、レノファ山口について深く知らない、
試合を見に行ったことがない方の回答も大変有意義なものとなります。
学生の皆様:
以下のGoogle formよりアンケート調査にご協力ください。
(回答には5〜10分程度かかります。)
なお、いただきましたご回答はすべて統計的に処理し、本プロジェクト以外の
目的に使用することはありません。
<回答フォームURL>
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvhUYcEIjILRO-pyYNCe8fgyqs
E1POPVZU2RWBVlQCnA5qow/viewform
アンケート実施期間:令和7年6月9日(月)~令和7年6月30日(月)
教職員の皆様:
授業やゼミの時間に学生さんへアンケートの回答を呼びかけていただければ
幸いです。ご協力をお願いいたします。
▼ 問い合わせ窓口はこちら ▼
山口大学学生支援部教育支援課教育連携係
TEL : 083-933-5032
E-mail : ga110@yamaguchi-u.ac.jp
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Voice -みなさまの声をカタチに-
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
情報・データ科学教育センターでは、学内外の方々と連携を進めながら
サービスを高めていきたいと考えております。
この度、教育連携係の室川係長がご異動されることになりました。
室川係長には、当センターの事務方トップとして、日々の事務処理はもちろんのこと、
センターの企画や運営に関しても、常に的確なサポートと貴重なアドバイスをいただ
きました。室川係長のご貢献は、本センターにとってかけがえのないものであり、
センター教職員一同、深く感謝しております。本当にありがとうございました。
新しい部署での室川係長の益々のご活躍を心よりお祈り申し上げます。
数理・データサイエンス・AIに関連するご意見やご要望などが
ございましたら、下記の連絡先までメールか電話でご連絡ください。
ご協力をよろしくお願いいたします。
=== 最後までお読みいただき、ありがとうございました。 ===
▼ バックナンバーはこちら ▼
https://www.dsc.yamaguchi-u.ac.jp/category/mailmagazine/
〇編集・発行 山口大学情報・データ科学教育センター
メール:dsm@yamaguchi-u.ac.jp
ウェブ:https://www.dsc.yamaguchi-u.ac.jp/
電 話:083-933-5986(内線:5986)