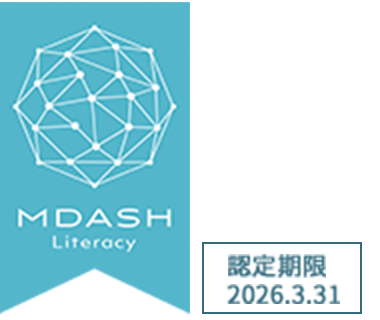[ 第12号 ] 株式会社 Fusic/DS講座マスターコース(2期生)履修証明書授与式/レノファプロジェクト最終報告会
─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…
山口大学情報・データ科学教育センター メールマガジン
第12号・2022年3月発行
─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…
教職員、学生の皆さま、こんにちは!
情報・データ科学教育センターです。
日ごとに春めいてまいりましたが、皆様お変わりございませんでしょうか。
桜の開花宣言が各地から聞こえてきました。
いよいよお花見シーズンの到来です。
桜の開花予想に使われている「600℃の法則」をご存じでしょうか?
「2月1日以降の最高気温を足し算していき、累積温度が600℃を超えた日に
桜が開花する」というものです。
平均気温の累積温度が400℃を超えた日という法則もあるそうです。
開花を待ちわびているうちは楽しいですが、開花してしまえば、あっという間
に散ってしまうのが桜です。平安時代の歌人 紀友則(きのとものり)は
ひさかたの光のどけき春の日にしづ心なく花の散るらむ
と詠いました。儚く散ってしまう、その光景に、この世の万物が絶えず変化し
続けていること、そして、形あるものは必ず滅することに思い至ります。
だからこそ、今この瞬間を大切にしなければならないと感じている今日この頃です。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「データ科学と社会II」のビデオ教材のご紹介
~テクノロジーが前提となる社会で生きていくために重要な掛け算の視点~
株式会社Fusic
取締役副社長 浜崎 陽一郎 様
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
2012年にDeep Learning登場以降、AIの現実的な活用が可能になり、続くCOVID-19
の発生とそれに伴う非接触・非対面の潮流が背中を押す形になり、今世界では、
AIを中心としたテクノロジーによるビジネスの刷新が急速に進んでいます。
つまり「テクノロジーが前提となる社会」に着々と向かっていると言えます。
その只中で、AIやクラウドコンピューティング、量子コンピュータ等を事業の
中心に据える僕らが、テクノロジーの現在地、つまり社会やビジネスの現場で
テクノロジーがどこまで活用されているのかをお話します。
さらにテクノロジーの過去・現在・未来を線で捉え、これからテクノロジーは
どんな可能性を秘めているのか、
今後の展望にも触れたいと思います。
一方「AIは人の仕事を奪うのでは?」といった質問をよくされます。
それに対する僕なりの回答と共に、これからテクノロジー前提の社会に飛び込む
学生の皆さんに何が求められているのか、そのために必要な行動とは何なのかを、
本講義でお話しします。
▼ ビデオ教材はこちら▼
https://www.dsc.yamaguchi-u.ac.jp/moviedata/po-login/03econo_01_fusic/210620_yamaguchi.mp4
▼ 株式会社Fusic様のリンクはこちら▼
https://fusic.co.jp/
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
データサイエンス技術マスター講座(2期生)の履修証明書授与式を
行いました
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
3月25日(金)、山口大学情報・データ科学教育センターにおける履修証明
プログラム「データサイエンス技術マスター講座」の履修証明書の授与式が
行われ、修了認定者10名のうち5名が出席されました。本講座は、山口県内
におけるデータサイエンスの活用を推進するため、山口県と連携し、履修証明
プログラムとして開講された講座で、企業活動においてAI、IoT、ビッグデータ
の先端的技術の利用が求められる中、高度なデータの分析・解析手法である
確率統計から機械学習までの分野を講義と実践的な演習を通して、企業において
データサイエンスを活用できるスキルを身に付けることを目的としています。
修了認定者は、令和3年5月から令和4年1月にわたって行われた90時間の
授業をすべて修了されました。授与式では、山口センター長から出席者に履修
証明書が授与され、本講座で学んだことを今後活かしていただくとともに益々
の活躍を祈念しますと挨拶がありました。
授賞式の後、修了生と山口県商工労働部秋重主査、本学松野理事・副学長、
川村リカレント教育部会長を交えて意見交換を行いました。和やかな雰囲気の
もとで話し合いが進み、理論から実践までじっくり学べることが本講座の強み
であることや、社会人ならではのご要望をお聞きすることができました。
これからの授業実施にフィードバックしていく予定です。
また、本講座は、本学の学生も受講しており、全課程を受講し修了した
学生4名に対しては、3月15日(火)に受講証を授与しました。
▼ 履修証明書授賞式の様子はこちら▼
https://www.dsc.yamaguchi-u.ac.jp/news/220325news/
▼ 受講証授賞式の様子はこちら▼
https://www.dsc.yamaguchi-u.ac.jp/news/220118/
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
レノファ山口ファンマーケティングプロジェクト
令和3年度最終報告会を開催しました
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
情報・データ科学教育センターでは、データサイエンスの教育プログラム
の一環として、レノファ山口及び山口県と連携して、データサイエンスを
応用し、レノファ山口のファンマーケティングに取り組む教育プログラム
を実施しています。本年度の最終報告会を3月24日(木)に開催しました。
山口県商工労働部企業立地推進課高林統括官の開会のご挨拶に続き、2つの
学生チームからプレゼンテーションがありました。
廣澤勇樹さん、藤澤耕平さん、多田晟人さんのチームは「観戦シート提案システム」
を発表しました。「離脱者を減らす」という課題と、「当日券購入者の割合
が想定以上に多い」というデータに基づき、「当日券の購入列に並んでいる
間の隙間時間に手持ちのスマホで簡単なアンケートに答えるだけで、最適な
観戦シートを提案するシステム」です。
中原祥喜さん、高司涼平さん、小島拓也さんのチームは「サッカー観戦者に
おける交流アプリ」を発表しました。新しい観客の獲得や再来場者を増やす
ため、新たな観戦方法としてアプリ利用者が勝利チームやMVPへの投票、
実況チャンネル等で気軽に交流が行えるシステムです。
プレゼンテーションの後に質疑応答を行いました。
レノファ山口の内山運営部長から実務者の視点でコメントいただきました。
また短時間でアイディアをかたちにし、試用評価まで行っていることを
お褒めいただきました。
閉会式では本学松野理事・副学長から発表学生へプロジェクト活動を通じて
学んだことを今後活かしていただくとともに益々の活躍を祈念しますと
挨拶がありました。
レノファ山口様にはビジネス上の課題やデータを惜しげもなくご提供下さり、
また学生の質問にも丁寧にご回答いただきましたことをこの場をお借りして
重ねて感謝申し上げます。
本プロジェクトは令和4年度も発展的に継続します。当該プロジェクトにご関心
のある方はセンターへご連絡ください。
▼ 最終報告会の様子はこちら▼
https://www.dsc.yamaguchi-u.ac.jp/news/220324news/
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
データサイエンス講演会の講演ビデオ視聴のご案内(5月末日まで)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
3月2日付のメールでご案内していますように
3月1日に開催しましたデータサイエンス講演会の講演ビデオを、学内限定で
令和4年5月末日まで公開しています。
(視聴可能期間を延長しました。)
まだご覧になっていない方がいらっしゃいましたら、ぜひこの機会にお急ぎ
ご視聴ください。
題目:「デジタルトランスフォーメーションの本質と、地域活性化への適用」
経済産業省のDXレポートの紹介や、地方におけるDX推進のポイント等
をお話いただきました。
講師:赤津 雅晴 氏
(株)日立システムズ 執行役員 CTO 兼 経営戦略統括本部 統括本部長
経済産業省の「デジタル産業の創出に向けた研究会」委員を務められ
ており、我が国を代表するDXの専門家。
視聴をされる場合は、以下のURLにアクセスし、本学アカウントにてログイン後、
視聴してください。
https://ds0n.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~kdev/gakunai/po-login/20220301/2022-03-01-09-57-20.mp4
注:視聴は学内限定です。録画や学外者が閲覧できる環境への持ち出しは禁止です。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Voice -みなさまの声をカタチに-
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
お知らせがございます。
このたび、情報・データ科学教育センターの事務を担当してくださっていた
中野さん、細川さん、宮田さんが2022年3月31日をもって退職することとなりました。
センター創設期の大変な時期に膨大な事務作業をいつも笑顔でご対応いただき、
心から感謝いたします。3人の皆様の今後のご活躍を心よりお祈りいたします。
なお、4月1日以降は後任として、山内さんにご支援いただきます。
情報・データ科学教育センターでは、学内外の方々と連携を進めながらサービス
を高めていきたいと考えております。
数理・データサイエンス・AIに関連するご意見やご要望などがございましたら、
下記の連絡先までメールか電話でご連絡ください。
ご協力をよろしくお願いいたします。
=== 最後までお読みいただき、ありがとうございました。 ===
〇編集・発行 山口大学情報・データ科学教育センター
メール:dsm@yamaguchi-u.ac.jp
ウェブ:https://www.dsc.yamaguchi-u.ac.jp/
電 話:083-933-5986(内線:5986)