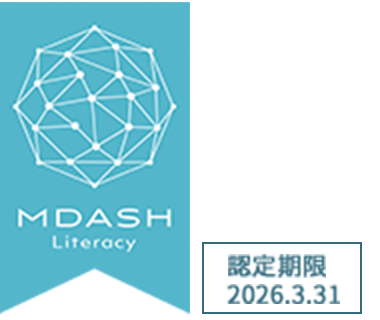「AI 技術×〇〇」研究デザインプロジェクト(2023年度~2024年度)
◆ 頚動脈エコー情報に基づく脳循環予備能推定システムに関する研究
〈 研究代表者 〉
河野亜希子(医学部脳神経外科・助教)
〈 研究の概要 〉
脳梗塞の原因の一つである内頚動脈狭窄症に対する治療を行う際に、脳循環予備能を評価して治療後の合併症リス
クを予測します。この際、薬物負荷を用いたSPECT検査を行っていますが、これは高価で副作用のリスクもあり、
実施施設も限られる検査です。本研究では、安価で非侵襲的な頚動脈エコー検査により得られたデータから、機械
学習を用いて脳循環予備能を予測することで、SPECT検査の代用として活用できる可能性を探りました。臨床応用
に向けてその予測精度を高めるべく研究を行いました。
AI研究デザインプロジェクト ( 2021年度~2023年度 )
◆ 医療過疎地における急性期脳卒中診療の均てん化 ~AI診断システムの開発~
〈 研究代表者 〉
藤井奈津美(医学部脳神経外科・助教)
〈 研究の概要 〉
医療過疎地での急性期脳卒中診療にAIを導入すべく研究を行いました。他院から送られてきた脳出血患者の画像を
用いて、手術適応を機械学習させました。CT値が必要であり転送画像にはCT値がないため初年度はうまくいきませ
んでした。判断材料になる画像を減らし、患者背景や出血部位を追加し、機械学習を再度させて検証を行ったとこ
ろ、約75%の適合率と再現性を確保することができました。実臨床に応用することはまだ困難な段階ですが、今後
臨床に活用すべく研究を継続中です。
◆ IT×自然教育の支援AI発達診断技術開発
〈 研究代表者 〉
小柴満美子(創成科学研究科・准教授)
〈 研究の概要 〉
機械・情報のバーチャル技術発展に伴い “人間性の涵養”に関する混迷状態が社会課題として知られるようになり
ました。そこで、人類の生存できる実空間とバーチャル空間の相互作用を促すIT/AIと生物を支える自然や食との
融合システムの開発デザイン方向を探り、地域社会フィールドでその検証を進めました。地域で愛されるマスコッ
ト映像に変化を与える脳神経の新成長支援システムの可能性や、画像識別AI、テキストマイニングAI等を活用した
心理機能推量や食育などを提案し、定量情報に基づく検証を行いました。
◆ 細菌の分泌機構から分泌されるエフェクタータンパク質の推測と機能解析
〈 研究代表者 〉
清水隆(共同獣医学部・准教授)
〈 研究の概要 〉
細菌のVI型分泌機構から分泌されるタンパク質(エフェクター)を同定するために、決定木によってアミノ酸の
共通配列を探索するBONSAI、複数のデータベースの横断的検索から病原因子を予測するPathoFactによる推測を
行いました。人獣共通感染症の原因菌である野兎病菌のゲノムを解析した結果、BONSAIとPathoFactでの推測に
共通して見られる4遺伝子をエフェクター候補とし、これらの遺伝子について遺伝子破壊株を作成し、野兎病菌の
病原性への関与に係る研究を行いました。

データサイエンス文化醸成のための
AI技術研究交流促進プロジェクト( 2019年度~ 2021年度)
- AI技術を用いた虐待が疑われる児童の医学的判別のためのシステム構築
研究代表者:髙瀬泉 - 微生物の細胞レベルでの凝集性の評価を可能にするAIの開発とその利用
研究代表者:高坂智之 - UAV画像(ドローン映像)と環境DNA情報を統合した水生生物(アサリ)生息場の識別システムの構築
研究代表者:間歩真吾 - AI技術の妊婦検診データへの応用による妊娠合併症予測システムの開発
研究代表者:前川亮